都築 尊 教授 インタビュー
――先生のご出身と、幼少期はどのように過ごされてきたのかお聞かせください。
都築:出身は愛媛県八幡浜市です。海と山に囲まれた小さな町で、幼い頃は釣りをしたり、山道を自転車で走り回ったりしていました。プラモデルも好きで、パーツにろうそくの火を当てて曲げ、オリジナルのポーズをつけるなど工夫して遊んでいました。
――手先が器用だったのですね。歯科医師のお仕事にも繋がりがありそうですが、歯科医師への道を進まれたきっかけは何ですか?
都築:実家が歯科診療所で、小さなころから父親が診療している姿を間近に見てきました。1階の半分が診療所だったのですが、技工室が遊び場のような感じで金属を溶かして遊んでいました。若い技工士さんによく遊んでもらっていたので当時から義歯(入れ歯)はよく見ていましたね。お正月でも急患対応している父親の姿や、子どもながらに「歯が痛い」といって診察に来た方の苦痛が取れて帰っていかれる姿を見て、人の苦しみを取り除く魅力ある仕事だと感じました。
――ご卒業後にご実家の歯科医院に戻られる選択肢もあったと思いますが、そうではなく大学院へ進まれたのはなぜでしょうか?
都築:やはり実家は田舎で高齢者が多いため義歯のニーズがとても高いです。このためもっと義歯の勉強をしたほうがいいと考えたことがひとつ、もうひとつは学生時代ヨット部に所属していたことです。
部活の顧問だった羽生哲也先生が現在の所属である咬合修復学講座有床義歯学分野の教授でしたのでご縁があり今に至ります。当時はヨット部のOBに有床義歯学分野の先生方が多かったので進路について相談しやすかったですね。大学の同窓会もそうですが、同門の縦の繋がりや仲間との横の繋がりが強いことが本学の特徴だと思います。
――当時(大学院生時代)の研究と今の研究はつながりがあるのですか?
都築:当時は骨に関わる基礎研究に取り組みました。顎の骨や歯肉は義歯を支えるために非常に重要です。重力であったり、ものを食べたりする際に刺激を受けることで顎の骨が強くなるのですが、骨にかかる負荷や咬み合わせの力による刺激について研究を行いました。
(歯の模型)
都築:今の研究はその地続きになるのですが、咬み合わせから発展して認知症の進行を抑制するような効果があるか、また認知機能の維持に繋がるのかを研究しています。研究にはスタッフとして大学院生も頑張ってくれています。
――活発に研究に励まれる大学院生も育っている様子ですが、本学で教授として教育に携わり、医科歯科総合病院の副病院長としても勤務する中で学生への指導方法が時代とともに変化した点はありますか?
都築:そうですね、本学は学生と教職員の距離が近いことが大きな特徴だと思っているのですが、この8月に完成する予定の新しいキャンパスは、建物の構造上さらに学生と教員が接する機会が増えるように設計されていると聞きました。今まで以上にフランクに学生との交流が増え、質問や相談に応じることができると楽しみにしています。教育に携わりだして間もない頃はとにかく「勉強しなさい」と言うタイプだったのですが、現在では学生にどのように勉強に対するモチベーションをつけてもらうかを考えて、自分自身が関わり方を変えるようになりました。教材に動画や模型を作ったり、教科書は1冊に絞ったり、プリントは1枚ですっきりまとめるなど、思いつくことは常に工夫しながら学生ひとりひとりと向き合っています。
――学生がわかりやすいように工夫されていますね。5年生になると勉強以外にも臨床実習がありますが、どのような指導を心掛けておられますか?
都築:学生が参加するという点を一番意識して取り組んでいます。患者さんに対してプロフェッショナルとして接することを学んでもらうのはもちろんなのですが、特に心掛けているのは指導医としての自分の診療に「携わってくれてありがとう、あなたがいて感謝しています」という気持ちを学生へ伝えるようにしています。医療はチームで行うため仲間意識を持ってもらうように指導しています。また、臨床実習に限らず全ての学年の学生に心掛けているのは「本気を見せること」ですね。「自分は本気で学生に向き合っているよ」という気持ちを心から伝えるようにしています。「一緒に勉強頑張ろう」となるように、だから教材作成も本気で取り組んでいますし、質問や相談には本気で応えています。
自身の専門分野である補綴や義歯は、静止画や紙面、文章で読んでも理解しづらいと思います。学生が質問や相談に来てくれた時は、理解を深めるための動画を作ったり、模型を学生の前で動かして説明したりして理解してくれるまで何回でも繰り返します。この積み重ねで本気度が伝わると思っています。
――最後に、受験生の皆さんにメッセージをお願いします!
都築:日本は今、超高齢社会を迎えています。高齢者の方たちが増えているのと同時に、認知症の方も増えています。人生100年時代と言われますが、私たちはしあわせな人生100年時代でなければならないと考えています。私たちは、人生100年時代をもっとしあわせな人生100年時代にしたいと夢をもって仕事をしています。そのために歯科医師ができることは必ずあるはずです。
入れ歯が合わなくて食事が楽しくなくなると、人に会うことや外出することを避けるようになってしまいます。そうなると、家に引きこもってしまいます。その孤独感が認知症の発症を進めてしまいます。
私たちは、お口の健康を通して認知症を無くし、しあわせな人生100年時代を創造したいと考えています。そのために、歯学を学ぶ若い人たちを沢山求めています。
どうか一緒に、歯学の道を志しましょう!
――今日は貴重なお話をお聞かせくださりありがとうございました。

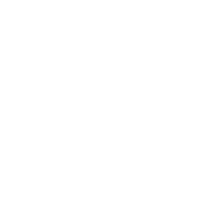



__large.jpg)
__large.jpg)
