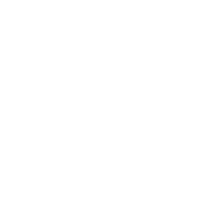2025.09.17 【研究成果】「口腔セネストパチー」の対処行動が脳活動を変化させるメカニズムを解明
福岡歯科大学 総合歯科学講座 高齢者歯科学分野の梅﨑陽二朗准教授と東京科学大学 歯科心身医学分野の豊福明教授らの研究チームは、歯科心身症の1つである「口腔セネストパチー(Oral Cenesthopathy)」の患者さんにおいて、自覚症状が一時的に緩和する「対処行動(coping behavior)」を行った際の脳血流変化をSPECT検査で解析しました。
その結果、「対処行動」で自覚症状が緩和している時には、もともと確認されていた右側優位の脳血流(regional cerebral blood flow: rCBF)の左右差がむしろ拡大するという、従来報告されてきた治療によって左右差が解消するという傾向とは逆の脳活動の変化が確認されました。
この研究成果は、国際学術誌 Frontiers in Psychiatry(2025年9月2日) に掲載されました。
本研究のポイント
■ 口腔セネストパチーの自覚症状緩和時に脳血流の左右差が拡大
口腔セネストパチー患者では、ガムを噛む・水を飲むなどの「対処行動」により自覚症状が一時的に緩和すると、右脳優位の脳血流の左右差がさらに強まることを発見しました。これは、薬物療法などが奏功すると脳血流が沈静化するという、従来の報告とは逆の現象として観察されました。
■ 「異常状態への適応」を反映する脳活動の可能性
自覚症状が楽になることが必ずしも「病的な脳活動の正常化」を意味せず、異常な感覚状態に適応するための二次的な脳活動である可能性を示しました。
■ 高次視覚野の関与と病態理解への示唆
今回の結果では紡錐状回や海馬傍回など高次の視覚情報処理に関わる領域が活性化しており、患者さんが口腔内の「異物感」をリアルに図示できる現象と関連している可能性を示しました。
本研究の詳細はこちら(pdf)
<研究に関するお問合せ>
福岡歯科大学 総合歯科学講座高齢者歯科学分野
梅﨑 陽二朗
Mail: umezaki■fdcnet.ac.jp
<報道に関するお問い合わせ>
福岡歯科大学 企画課企画広報係
Mail: kouhou■fdcnet.ac.jp
※ご連絡の際は、■を@へ変更してください。