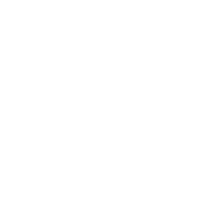医療人間学講座について
講座概要
医療人間学講座は、社会・基礎医歯学部門に属し、言語情報学、医療倫理学、医療心理学の3分野から成っています。この講座は2001年の教員組織改革に伴い、それまでの哲学・倫理学、経済学、英語、ドイツ語の4講座が統合・改編されたものです。
主任教授挨拶
医療人間学講座医療倫理学分野 教授 永嶋 哲也
医療人間学講座には、文系の専任教員が属する二つの分野と医科の併任教員を擁する一つの分野があります。そのうち文系の言語情報学分野では英語をはじめとする外国語や国際理解を育成する授業を、そして、医療倫理学分野では倫理、論理、哲学等の身の回りのあらゆる事象を深く考える授業を担当しています。ふたつの分野が目指しているのは、学生の「人間としての心の成長」です。毎年、本学から多くの学生が医療人として巣立っていきますが、わたしは本講座の主任として、知識のみならず「人間力」のある医療人の育成をサポートしていきたいと思っています。
それぞれの名称をクリックすると、詳細情報に移動します。
言語情報学分野
教育の概要
言語情報学分野では、英語と必修選択科目としてドイツ語・中国語の教育を行っています。
英 語
英語教育では、将来、歯科診療に携わる学生の皆さんがEvidence-Based Medicine (EBM)に関する諸外国の情報を迅速かつ的確に入手できるように読解と英語会話に重点をおいた語学教育を行っています。授業科目としては、1~2年生を対象としたScientific EnglishとPractical Englishがあります。Scientific Englishでは、読解を重視した授業を展開し、医療関係のものから科学全般にわたる興味深い教材を通じて、語彙、文法、英文構成の基礎力の強化を図ります。Practical Englishでは、外国人講師が担当し、日常会話の教材を使用して、楽しい実践的な英語教育を行っています。令和3年度から4年生を対象としたGlobal Medical Englishが開講されました。この授業では、歯科の臨床に役立つ英語の会話表現や英語論文の読解のための基礎知識を取得することを目指します。
ドイツ語・中国語
ドイツ語・中国語は、1年生の後期に「ドイツ語I」および「中国語I」、2年生の前期に「ドイツ語II」および「中国語II」の講義名で、基本的な文法や読解等を行っています。
研究テーマ
1.医療英語指導のための映画活用法
映画を利用し、医療英語を学ぶ学生に向けた、英語の語彙、発話、イントネーションの効果的な指導方法の構築を目的とする研究。
2.異文化研究のための映画活用法
映画を利用し、学生の異文化理解を深める助けとなる指導方法の構築を目的とする研究。
言語情報学分野 所属教員
| 准教授 | 岡島 勇太 |
|---|
医療倫理学分野
歯科医師には、専門的な知識だけでなく、まっとうな人間としての良識や教養、倫理観などが必要とされます。そのようなものを育てるために大学には教養科目(リベラルアーツ)というものがあります。本学におけるそのような教養教育の一端を医療倫理学分野(旧 哲学・倫理学講座)は、になっています。

「自分のアタマで考える」ということ
・物事を論理的に(筋道だてて)考え、言葉にする。
・物事を根本から考え検討してみる。
・正しい、美しい、とはどういうことか考える。
・自分とは違った物差しで物事を考えてみる。
・医療と生命の場面で正しい、良いとはどういうことか考える。
とにかく自分のアタマで考えてみる、答えなど出ないかもしれないけれども考えてみる。そういうことを学び、訓練することで「人格の陶冶(とうや)」、つまりまっとうな人間への成長の出発点に立つことを目指します。
歯科医師として独り立ちしたあとに、一人の大人として成長し続けるための、遠大なる準備計画だと理解すればいいでしょう。
教育の概要
本分野で担当している主な教育は哲学・倫理学関係の科目である。「哲学」(1年前期)と「論理学・日本語表現法」(1年後期)、「医療倫理学」(2年前期)、「生命倫理学」(2年後期)などが主だった教科である。
「哲学」では、全学問の基礎(リベラルアーツ)として、ものごとを根本から論理的に考えるための訓練を行う。哲学史上の有名な学説や哲学者の名前などはあまり取り上げず、むしろ哲学上の問題そのものを取り上げ、紹介する。上の学年で開講される「医療倫理学」や「生命倫理学」で用いる基本的な概念装置を紹介するという側面もある。
「論理学・日本語表現法」では、日常言語による論理的操作のトレーニングを行う。推論に対して、論理構造を図示したり、その論証の確かさを確認したり、仮説形成において他の仮説の可能性を考えたり、というような練習問題を通して、文章を意識的に論理的に読み取り、自らも論理的な文章を組み立てるための能力を育てる。
「医療倫理学」は「倫理学」と呼ばれていた科目である。「尊厳」と「人格」をキーワードに、倫理学の基本的考え方を扱う。また、後期に開講される「生命倫理学」の理論的背景を紹介するという側面もある。
「生命倫理学」は、今日の医療場面で生じているさまざまな倫理的問題を扱う。何がどのような仕方でどのような理由で問題となるのかを紹介し、学生一人一人が自分自身で考えるための下地を作ることを目標としている。

研究テーマ
1.存在と真理の問題に関する、意味論の観点からの言語哲学研究
西欧中世の論理学(言語哲学)の場面で交わされた普遍論争を中心に、一般者の存在や一般名の意味について哲学・哲学史的な考察を行う研究。
2.個の尊厳に関する、人格の観点からの倫理学研究
現代の医療倫理学の文脈において言及される「尊厳」という語を中心に、人間の自由意志存在の問題から医療倫理学における自律尊重の根拠までを考察する研究。
3.恋愛の文化的範型に関する、思想史的観点からの文化論研究
西欧中世における「愛の誕生」の問題を中心に、キリスト教神学や中世文学、古代哲学の継承などについて思想史、文化史的に考察を行う研究。
医療倫理学分野 所属教員
| 教授 | 永嶋 哲也 |
|---|
医療心理学分野
医療心理学分野は、人間として、また医療人として大切な「心」の領域を教育研究する分野です。医療技術が高度化、細分化する一方で、ますます重要性が増してきた精神面について基礎から臨床までを教育します。とくに医療の基本となる患者医療者関係を結ぶための医療コミュニケーションの技術と態度を教授します。対象者(患者様)の心理社会面、行動面を含めた統合医療が実践できる医療人を育てることを目標としています。
研究テーマ
おもに臨床面から、心身症にみられる心身相関のメカニズムについて、自律神経機能の面からの研究しています。さらに、歯科領域の心身症や歯科治療に係わる急性、慢性の痛みについても研究しています。
1. 心因性発熱
心因性発熱の中枢・末梢メカニズムに関する研究
2.慢性疲労症候群
慢性疲労症候群の診断マーカーの確立
3.歯科領域の心身症
舌痛症、顎関節症、口腔内異常感症、義歯神経症、歯科治療恐怖症などの歯科心身症について、診断と治療におけるEBMの確立
4.睡眠、生活とストレス、疾患の関連について
心身症における生活習慣、睡眠障害についての疫学的調査
医療心理学分野 所属教員
| 教授 | 金光 芳郎(併任) |
|---|---|
| 助教 | 田中 佑(併任) |