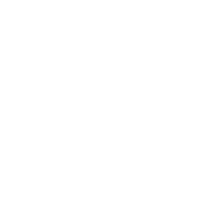口腔治療学講座について
講座概要
口腔治療学講座は、2大口腔疾患である「う蝕」と「歯周炎」、そして、主としてう蝕に継発して生じる「歯髄炎」、「根尖性歯周炎」の治療に関する学問分野を受け持っています。
主任教授挨拶
口腔治療学講座 歯科保存学分野 教授 松﨑 英津子
口腔治療学講座は、歯科保存学分野と歯周病学分野から構成されています。口腔医学の進展に寄与する歯科医師を育み「未来につなぐ」という考えのもと、講座の総力を挙げて卒前・卒後教育に取り組んでいます。
一方、研究面において、歯科保存学分野では、予知性の高いう蝕治療および歯内療法の基盤構築を目指し、象牙質−歯髄複合体および歯槽骨の再生機構をテーマとして、基礎と臨床を橋渡しできる研究を実施しています。また、歯周病学分野では、口腔医学の視点から歯周疾患の検査、診断、治療を網羅するようテーマを設定し、特に失われた歯周組織の再生に力を入れています。
当講座が担う歯科保存治療やそれにかかわる口腔医学研究が、「健康寿命の延伸」およびSDGs項目のひとつである「すべての人に健康と福祉を」へ貢献できるよう、日々邁進して参ります。
それぞれの名称をクリックすると、詳細情報に移動します。
歯科保存学分野
歯科保存学分野は口腔治療学のなかで、主に保存修復学と歯内療法学を担当しています。保存修復学は齲蝕(むし歯)や歯の損耗(tooth wear)および外傷などによる歯質の欠損を修復し、その歯を口腔内に維持する方法を考究する学問です。また、歯内療法学は歯質の欠損に続発する歯髄病変・根尖性歯周炎の予防・診断・治療について考究する学問です。歯科保存学分野では、これらの歯の保存治療の基盤となる領域を担当しています。
当分野では、予知性の高い新たな齲蝕治療および歯内療法技術の開発を目指して、組織化学的、生化学的、分子生物学的手法を用いて、「象牙質の修復・再生」および「骨組織の修復・再生」をテーマとする研究活動を行っています。
教育の概要
第3学年
齲蝕学Ⅰ、歯内療法学
第4学年
齲蝕学Ⅱ
保存修復・歯内治療実習
第5学年
臨床実習Ⅰ
第6学年
臨床実習Ⅱ 臨床演習(歯科保存(修復)学・歯内療法学)
研究テーマ
・脂質メディエーターを用いた象牙質歯髄複合体および歯周組織の再生に関する研究
・脂質メディエーターを用いた象牙質歯髄複合体の石灰化と老化に関する研究
・Bioactive Glassの歯内療法領域への応用
・根尖性歯周炎の破壊と治癒のメカニズムの解明
・根面う蝕の硬さと進行抑制に関する研究
歯科保存学分野 所属教員
| 教授 | 松﨑英津子 |
|---|---|
| 講師 | 松本 典祥 |
| 講師 | 水上 正彦 |
| 助教 | 松本 和磨 |
| 助教 | 廣瀨 陽菜 |
歯周病学分野
生物学をベースとした歯周病学の教育
歯周治療学を中心とした歯科保存学の教育を担当しています。
卒前教育の目標は,3年次から4年次にかけての講義,4年次模型実習,5年次から6年次にかけての臨床参加型登院実習を通じて,歯周疾患の病理を理解し,的確な診断を行い、優れた治療計画をたてることができる歯科医師を養成することです。科学的な診断は基礎医学科目の知識なしに成り立たないので,それらとの関連性を重視した講義・実習を行うことを心がけています。
教育の概要
第3学年
歯周治療学Ⅰ
第4学年
歯周治療学Ⅱ
歯周治療学実習
第5学年
臨床実習Ⅰ
第6学年
臨床実習Ⅱ 臨床演習(歯周病学)
卒後の臨床研修における歯周治療学の教育
卒業後の臨床研修においては、歯周基本治療から歯周外科処置、メインテナンスについて豊富な臨床経験を持つことができるよう,カリキュラムを編成しています。
研究テーマ
臨床にはじまり、臨床を指向する研究をテーマに、できるだけ臨床に結びついた研究、成果を社会に還元できる歯周病に関連した研究を心がけて行っています。
主なテーマ
・歯周炎発症・進行への老化細胞の関与
・咬合性外傷による歯周組織破壊促進のメカニズムの解明
・FGF-2製剤の歯肉軟組織への影響
・セメント質および歯槽骨形成の共通促進因子を応用した歯周組織再生療法の開発
・メタボリックシンドロームの歯周炎進行への影響
・歯周ポケット形成のメカニズムの解明
歯周病学分野 所属教員
| 教 授 | 吉永 泰周 |
|---|---|
| 講 師 | 大城 希美子 |
| 講 師 | 丸尾 直樹 |
| 助 教 | 大和 寛明 |